本記事は一部アフィリエイトプログラムによる収益を得ています。
本記事は【広告】を含みます。
自動車保険料率クラスとは?ワースト車種は?人気車種を徹底比較
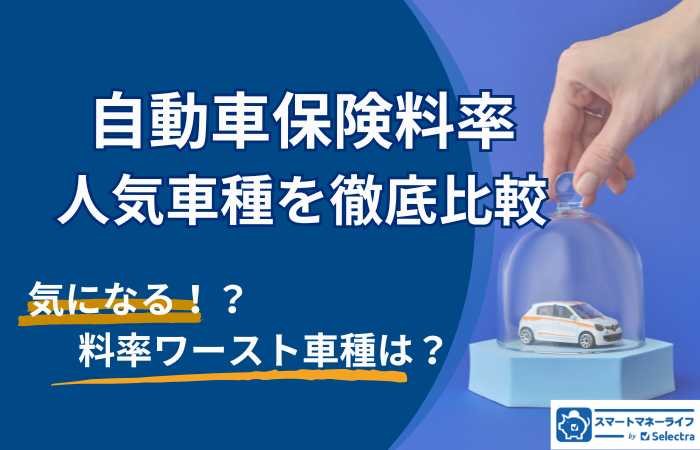
人気車種の料率クラスのワーストランキングを紹介! 自動車保険の型式別料率クラスは、保険料を公平に設定するための重要な仕組みです。 保険料率の仕組みを少し頭に入れておくと、保険会社の見積もりもわかりやすくなるかもしれません。ここでは2025年1月1日以降の契約に適用される最新の型式別料率クラスについて詳しく解説。保険会社の独自料率との違いについても詳しく解説します。
目次
人気車種の自動車保険料率ワーストランキング
まずは気になる車種ごとの料率クラスについて損害保険料率算出機構の料率クラスが高い順にワーストとしてランキングを作成しました。
\ 最安値の自動車保険を見つける/
3分で入力完了、無料一括見積もりへ
評価基準
2025年1月1日以降の型式別料率クラスの検索結果をもとに、対人・対物・人身・車両の料率クラスの合計が高いものから並べました。
注意!
保険料はクラスだけで決まるものではなく、保険会社の独自料率、車種・地域・契約条件などにも左右されます。同じ車種でも保険会社によって独自料率を適用するため保険料は違います。 あくまで目安としてのランキングであることをご留意ください。
普通・小型車:料率クラスの高い人気車種ランキング
| 順位 | 車種 | 型番 | 対人 | 対物 | 人身 | 車両 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アクア(トヨタ) | NP10 | 9 | 9 | 9 | 7 |
| 2 | プリウス(トヨタ) | ZVW60 | 7 | 6 | 9 | 9 |
| 3 | ヤリス(トヨタ) | MXPH17 | 6 | 7 | 9 | 9 |
| 4 | セレナ(日産) | GFC28 | 5 | 5 | 9 | 11 |
| 5 | ステップワゴン(ホンダ) | RP7 | 6 | 6 | 9 | 8 |
| 6 | ヴォクシー(トヨタ | ZWR95W | 5 | 5 | 8 | 7 |
軽自動車:料率クラスの高い人気車種ランキング
| 順位 | 車種 | 型番 | 対人 | 対物 | 人身 | 車両 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N-BOX(ホンダ) | JF6 | 4 | 4 | 6 | 4 |
| 2 | エブリイ(スズキ) | DA64W | 5 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | ジムニー(スズキ) | JB23W | 3 | 4 | 3 | 3 |
| 4 | タント(ダイハツ) | LA650S | 3 | 2 | 3 | 3 |
| 5 | ハスラー(スズキ) | MR52S | 2 | 2 | 3 | 3 |
比較車種の参考情報
比較車種の参考情報
ファブリカコミュニケーションズ│2025年1月自動車販売市場の動向(2025年1月)
日刊自動車新聞│2025年2月の車名別販売台数
MOTA│軽自動車新車人気車種ランキング
\ 同じ型式でも保険会社によって保険料が違う!/
自動車保険の無料一括見積もりへ
保険料率の仕組み
自動車保険の保険料は、契約者のリスクを反映する形で決定されます。事故の頻度や被害の大きさには、運転者の年齢や事故歴だけでなく、自動車の用途や種類による違いもあるため、さまざまな料率区分が設けられています。ここでは損害保険料率算出機構による型式別料率クラスについて解説します。
型式別料率クラスとは?
型式別料率クラスは、自動車の「型式」によってリスクを分類し、それに応じた保険料を適用する仕組みです。型式ごとのリスクは以下の要素に基づいて評価されます。
- 車両の形状、構造、装備、性能
- その車両を使用するユーザー層
型式とは
車検証に必ず記載されています。自動車を分類する公的な単位です。 たとえば ホンダフリードなら5BA-GT1→「GT1」が保険料率を確認するときの型式になります。
自動車の型式ごとに、過去の保険データ(事故発生率や損害額)を基にリスクを分類し、クラス(1〜17)を設定します。このクラスは、以下の4つの補償ごとに分けられています。
- 対人賠償責任保険
- 対物賠償責任保険
- 人身傷害保険
- 車両保険
リスクの高い型式はクラスが高くなり、保険料も高くなります。
料率クラスの区分について
型式別料率クラスは、自動車のリスクを数値化し、クラスごとに保険料を決定する仕組みです。
クラスの分類
自家用乗用車(普通・小型):クラス1~17(最も安いのがクラス1、最も高いのがクラス17)
- クラス間の保険料率の差は約1.1倍
- クラス1とクラス17の間では、最大で約4.3倍の保険料差
自家用軽四輪乗用車(軽自動車):クラス1~7(最も安いのがクラス1、最も高いのがクラス17)
- クラス間の保険料率の差は約1.1倍
- クラス1とクラス7の間では、最大で約1.7倍の保険料差
2025年1月1日から軽自動車の料率クラスが拡大
もともと軽自動車は型式別料率クラスがありませんでした。しかし2020年から料率クラスが3段階になり、2025年から7段階に細分化されました。
軽自動車の普及とともに、衝突被害軽減ブレーキ搭載などの機能搭載の進んでいる機種とそうでない車種などリスクにばらつきが出るようになったためです。
クラスの見直し
型式ごとのリスクを反映するため、毎年1月に「クラス見直し」が行われます。直近の保険データに基づき、リスクが高い型式はクラスが上がり、リスクが低い型式はクラスが下がる仕組みです。
- リスクが低い場合:「-1」または「-2」のクラスダウン
- リスクが高い場合:「+1」または「+2」のクラスアップ
- 発売後3年以上の型式では、リスクの程度によって「-3」や「-4」などの大幅なクラスダウンもありえる
新しく発売された型式には十分な保険データがないため、自家用乗用車は排気量や新車価格、発売年月などを基にクラスを決定し、自家用軽四輪乗用車は一律でクラス4を適用します。

料率クラスが高い=事故率が高い?
料率クラスが高いということは、その型式の車両におけるリスクが相対的に高いことを示しますが、「事故率が高い=危険な車」とは限りません。
クラスが高くなる要因
🤔事故率が高いということでないなら、なぜクラスが高くなるのでしょうか?
🚙車両の特性:高性能車や大型車は、事故時の修理費用や賠償額が高額になりやすい
👩ユーザー層の影響:スポーツカーなどは、若年層のドライバーが多いため事故率が高くなる傾向がある
クラスの上昇・下降は個人の事故歴とは関係ない
型式別料率クラスは、個人の事故歴ではなく、その型式の車両全体のリスクを基に決定されます。 そのため、自分が事故を起こしていなくても、その型式の車両全体のリスクが高まればクラスが上がり、逆に事故を起こしていても、型式全体のリスクが下がればクラスが下がることもあります。
クラスが高い=危険な車ではない
料率クラスの高さは、必ずしもその車が「危険」であることを意味しません。 なぜなら、クラスの決定にはユーザー層の特性も考慮されており、同じ性能の車でも異なるメーカーのOEM車ではクラスが異なることがあります。

損害保険料率算出機構の料率 vs 民間保険会社の料率
ここまで損害保険料率算出機構について解説しました。では保険会社では全く同じ料率を使っているのでしょうか? 実は民間保険会社では公的な料率を参考にしつつも、各社の持っている情報やデータから独自の料率を適用しています。
型式別料率クラスと保険会社の料率の違い
| 項目 | 損害保険料率算出機構の料率 | 保険会社の料率 |
|---|---|---|
| 目的は? | 全国的な事故リスクを基に、公平な料率を設定 | ビジネス戦略や自社データを考慮し、独自の料率を設定 |
| 基準は? | 過去の事故データを基にクラスごとにリスク評価 | 参考純率を基に、地域や顧客ごとに細かく調整 |
| 調整できる? | 固定された「参考純率」 | 運転者情報・地域・特約などで自由に調整 |
| 更新頻度は? | 毎年1月にクラス見直し | 随時変更可能 |
損害保険料率算出機構が定める料率
損害保険料率算出機構は、日本全国の保険データを分析し、型式別のリスクを評価した上で「参考純率」を設定します。この「参考純率」は、保険会社が保険料を決定する際の基準として用いられます。
ポイント
- あくまで「参考値」であり、保険会社はこれをそのまま適用する義務はない
- 全国平均のデータを基に算出されるため、特定の地域や顧客層には完全に合致しないことがある
- 毎年見直しが行われ、最新の事故データを反映
保険会社が設定する料率
保険会社は、損害保険料率算出機構の「参考純率」を基に、独自の料率を決定します。保険会社ごとに異なる料率を設定できるのは、以下のような理由があるからです。
ポイント
独自の事故データを考慮
- 自社の契約者データを活用し、特定の顧客層に適した料率を設定できる
- 都市部と地方でリスクが異なる場合、地域ごとに保険料を調整
リスク細分化要素の追加
- 運転者の年齢・運転歴
- 年間走行距離
- 安全装置の装備(衝突被害軽減ブレーキなど)
- 使用目的(通勤・業務利用など)
これらの要素を加味して、最終的な保険料を決定できる。
ビジネス戦略
- 他の保険会社との差別化のため、利益率や契約獲得を考慮して料率を調整できる。
例えば、特定の車種に対して割引を提供することで、新規契約を増やす戦略などがとれます。

まとめ:同じ車種型式でも保険会社によって保険料は変わる
型式別料率クラスは、公平な保険料負担を実現するための仕組みですが、実際の保険料は保険会社によって異なります。 保険会社は、損害保険料率算出機構の参考純率を基に、独自の料率を設定し、リスク細分化を行います。
自動車の型式だけでなく、運転者の属性や地域などによって保険料は変動するため、同じ車種でも複数の保険会社を比較することは、より納得のいく保険選びでは非常に重要です。
出典ː 損害料率算出機構│自動車保険参考純率

