高額療養費制度とは?医療費が戻ってくる仕組みや申請方法について
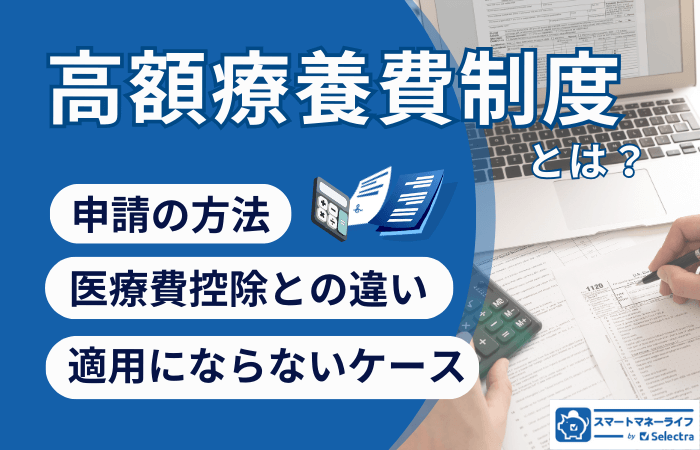
病院会計は3割負担ですが、それでも医療費が高額になった時に力を発揮するのが高額療養費制度です。1か月に支払う金額上限はいくら?どうやって計算するの?使えないパターンもあるの?さらに最近話題のマイナンバー保険証の便利機能についても解説します。
医療費に使える公的保険制度
日本は国民皆保険の国です。 自営業であれば国民健康保険、企業勤めであれば健康組合保険、引退していれば後期高齢者医療保険と、 健康保険の種類は違いますが、何かしらの公的保険に入っています。
この記事は2023年2月時点の最新情報から基本的な内容をまとめてお伝えします。
混乱しやすい主な制度:高額療養費?医療費控除?
「高額療養費制度」や「医療費控除」は用語が難しい上に、どちらもなんとなく手術や治療にかかった費用に関係ある。 というような印象を受けます。しかしその差は言葉だけではわかりにくくネット上でも混乱している様子が見えてきます。
・高額医療費は請求できません。医療費控除と間違えておりました。大変失礼致しました。
・これらを混同した問い合わせが確定申告の窓口では増えてめちゃくちゃ。
まず、病院や薬局に支払うお金が高額になった場合に、私たちが一般的に使う制度にはどのようなものがあるか整理しましょう。
- 3割負担
- 高額療養費制度
- 医療費控除
制度はもっと細かいものがあったり、年収や年齢によって負担する割合も変わります。こちらの記事では概要の理解を目的として一般的な制度を挙げて説明しています。
この3つの制度について特徴を表にまとめました。
病院・薬局などでかかる費用の3割の支払い。
| メリット | 名称 | 申請タイミング 申請可能期間 | 概要 |
|---|---|---|---|
| お会計が減る | 3割負担 | お会計ごと | |
| 高額療養費制度 | 1か月ごと 2年間申請可能 | 3割負担は上限まで ・3割の負担でも高額になる場合 ・「自己負担の限度額」以上に支払ったお金は戻ってくる。 ・もしくは請求されない | |
| 税金が減る | 医療費控除 | 1年ごと 5年間申請可能 | 所得税・住民税を減らす。 ・年間の医療費を所得から引く(控除)ことができる。 ・その分所得が少なくなるので、その年の所得税・住民税が減額できる。 |
高額療養費制度は病院窓口のお会計金額が減る。
医療費控除は支払う税金が減る。
3割負担でも医療費が高額な場合は、1か月単位で「高額医療費制度」を利用します。 そしてその年の最後にかかった医療費の総額が一定額以上であれば、「医療費控除」を申告する流れになります。
医療控除についてはこちらの記事で説明しています。是非参考にしてください。 医療費控除いくら戻ってくる?
この記事では高額療養費制度について説明していきます。
高額療養費制度とは?
日本国民はみんな何かしらの健康保険に入っていて、病院窓口や薬局で支払うお金は3割ですみます。 業種によって健康保険の種類は様々ですが、全てのひとが受けられる制度です。
しかし、それでもの手術・長期の入院・薬による治療などで病院や薬局へ支払う金額が高額になってくると、生活を圧迫します。
高額療養費制度はそんな時に力を発揮します。この制度によって私たちは1か月当たりの医療費の自己負担金額に上限が決められているのです。 つまりその上限金額を超えて支払ったお金は戻ってくるのです
自己負担額をここまで払ってくださいという上限金額は、その人がいくら稼いでいるかで決められています。
表の前提 ・「年収」「自己負担限度額」:厚生労働省保険局高額療養費制度を利用される皆様へを引用
・「ざっくりいくらまで支払う必要があるか」:総医療費100万円~300万円で計算した金額を千円単位で四捨五入。
| 年収 | 自分で払う上限金額 (自己負担限度額) | だいたいいくらまで 自分で払う必要があるか。 |
|---|---|---|
| 1,160万円~ 月収83万円以上 | 252,600円+(総医療費-842,000)✖1% | 25万円~27万円 |
| 約770万~約1,160万円 月収53万円~79万円 | 167,400円+(総医療費-558,000)✖1% | 17万円~19万円 |
| 約370万~約770万円 月収28万円~50万円 | 80,100円+(総医療費-267,000)✖1% | 9万円~10万円 |
| ~約370万円 月収28万円~50万円 | 57,600円 | - |
| 住民税非課税 生活保護・所得135万円以下など | 35,400円 | - |
高額療養費制度が必要になる時
高額療養費制度はどんな時につかえるのでしょうか。「医療費が高くなる」と言っても、その事情には違いがありますので、3つのパターンに分けて説明していきます。
- 医療費が高くなる可能性
- 短期の高額治療:一発の高額手術など
- 数名の高額治療:家族メンバーが同時期に病気にかってしまう
- 長期の高額治療:半年以上の長期治療が必要になる
解説の前提 ■2023年2月時点の情報を基にしています。
■年齢:69歳以下
■年収:約370万~約770万円
■制度が使えないケース:本記事の後半で解説
順を追って高額療養費制度の全体像が把握できるように説明していますので、是非全ての事例を読んでみてください。
短期の高額治療
短期の高額手術として、心筋梗塞など急を要する手術が挙げられます。
短期の治療たとえば・・・心筋梗塞でバイパス術が必要になった
治療 冠動脈バイパス術
心臓の詰まった血管に新しい血管をつなぎ、血の流れをよくする手術です。
費用 3割負担で約100万円 総医療費330万円
冠動脈バイパスは3割負担でも約100万円ほどの出費が必要になる手術です。「高額療養費制度」を利用した場合、いくらの出費に抑えることができるのでしょうか。先ほどの高額療養費制度の表から、支払い上限がいくらになるか確認してみましょう。
計算式 80,100円+(総医療費-267000)×1%
80,100円+(3,300,000‐267,000)×1% = 110,430円
3割負担で100万円の手術が 高額療養費制度を使用するとおよそ11万円に
数名の高額治療:家族の医療費は足し算できる(世帯合算)
扶養に入っているメンバーの治療費は高額療養費制度で足し算することができます。この足し算を世帯合算といいます。
数名の高額治療たとえば・・・夫の帯状疱疹と、高校生の子供のアトピー治療が重なった
夫と子供が同時期に治療が必要になった場合について考えてみます。
夫:帯状疱疹
治療 点滴8日
症状がひどいため入院して点滴を行います。
費用 3割負担で約10万円 総医療費33万円
高校生の子供:アトピー治療
治療 治療薬を注射
デュピクセントというアトピーに対する治療薬を月に3本注射します。
費用 3割負担で約7万円 総医療費23万円
夫と子供:医療費を合算
家族で医療費がかさんでしまった場合は、その月の医療費として合算することが可能です。
計算式 80,100円+(総医療費-267000)×1%
80,100円+{(330,000+230,000)‐267,000}×1% = 83,030円
家族合わせて3割負担で17万円の治療が 高額療養費制度を使用するとおよそ8万円に
長期の高額治療:年に3回以上高額の場合はさらに負担額が減る(多数回該当)
高額の医療費を軽減してくれるのはありがたいのですが、それでも8万円です。長期や回数を重ねる治療は非常に苦しくなることに違いはありません。
そこで、高額療養費制度では何回も治療が必要。薬が必要な場合にはさらに自己負担を減らすことができます。
この仕組みを「多数回該当」といいます。
「多数回該当」は直近12ヵ月間に既に3回以上高額療養費が支給されている場合に使えます。そして4回目から支払金額の上限はさらに減ります。
一体いくらになるかというのが下記の表です。
| 年収 | 自分で払う上限金額 (自己負担限度額) | 多数該当が使える場合の 上限金額 |
|---|---|---|
| 1,160万円~ 月収83万円以上 | 252,600円+(総医療費-842,000)✖1% | 140,100円 |
| 約770万~約1,160万円 月収53万円~79万円 | 167,400円+(総医療費-558,000)✖1% | 93,000円 |
| 約370万~約770万円 月収28万円~50万円 | 80,100円+(総医療費-267,000)✖1% | 44,400円 |
| ~約370万円 月収28万円~50万円 | 57,600円 | 44,400円 |
| 住民税非課税 生活保護・所得135万円以下など | 35,400円 | 24,600円 |
長期の高額治療たとえば・・・がんによるオプジーボ投与
治療 治療薬オプジーボ
がん治療に使用されるオプジーボという薬は、皮膚がん、肺がん、胃がんなど幅広く使われます。
費用 3割負担で半年約270万円 総医療費900万円
オプジーボは超高額な治療薬でたとえば1か月のうち数回に分けて1回240mgを投与します。100mgで155,000円ですので、1回あたり約37万円。1ヵ月で4回投与のスケジュールの場合、合計約150万円となります。例えば6か月投与した場合、総医療費で半年合計900万円となります。****
そこで高額療養費制度を使用します。毎月約9万円を6ヵ月繰り返しますので、半年で約54万円となります。
9万円が6か月も続くのは負担が大きいため、多数回該当によって支払う金額をさらに減らすことができます。高額療養費制度を年3回使用した時点で、4回目以降は多数回該当の金額が上限になりますので、この場合上限4万円となります。
計算式
1.高額療養費制度で計算した1か月あたりの支払限度額
80,100円+(総医療費-267000)×1%
80,100円+(1,500,000‐267,000)×1% = 92,430円
2.高額療養費制度を年間3回使用したため、4回目以降の限度額
44,400円
3.6ヵ月に支払う医療費の合計金額
92,430円×3回 + 44,400円×3回 = 410,490円
3割負担で半年270万円の治療が 高額療養費制度の多数回該当を使用するとおよそ40万円に
治療費の情報参照:
*心筋梗塞によるバイパス術医療法人徳洲会名古屋徳洲会総合病院:心臓血管外科手術について
**帯状疱疹による点滴中部電力株式会社中電病院:手術費用等概要一覧
***アトピー治療薬あいづ皮ふ科クリニック:一般皮膚疾患治療
****がん治療薬小野製薬:オプジーボ治療
がん治療費.com
さらに長期の高額治療たとえば・・・・HIV・血友病・人工透析
治療に必要な時間が非常に長く、続けて治療を行うことが必要な病気には多数回該当の特例があります。
- HIV・血友病:自己負担上限1万円
- 人工透析:自己負担上限1万円または2万円(年収による)
高額療養費制度の申請方法は?申請しなくても戻ってくる?
いざ治療費が高額になった、高額療養費制度はどのような方法で利用できるのでしょうか?
| 方法 | 会計前👉 | 👉窓口での会計👉 | 👉会計から3か月以降 |
|---|---|---|---|
| 事後申請 | - | ・3割負担分の費用を支払う。 ・健康保険に申請 | ・高額療養費制度の自己負担上限額を超えた分のお金が戻ってくる。 |
| 事前申請 限度額適用認定証 | 健康保険に限度額適用認定証を発行してもらう | 高額療養費制度の自己負担上限額までを支払う。 | - |
| 申請不要 マイナンバー健康保険証 | - | 高額療養費制度の自己負担上限額までを支払う。 | - |
それぞれの方法について、流れとデメリットを説明していきます。
事後申請
まずは窓口で3割負担分を支払います。その後自分の加入している健康組合へ高額療養費制度を利用したいと申請します。
申請の方法は健康保険ごとに差がありますが、必要な書類はシンプルです。
・申請書
・領収書(不要な場合もある)
申請から3か月以降、高額療養費制度の自己負担額を超えて支払っていたお金が指定口座に振り込まれます。
事後申請のデメリット
先に高額の支払いが発生するため、問題はお金が戻ってくるのかという不安と現金不足です。
- 不安:本当に入金があるか。ドキドキする。3ヵ月以上待つのが怖い
- 現金:高額の支払いがあったため、貯金が一気に減った。振り込まれるまで待つのが痛い。
事前申請:限度額適用認定証
手術や高額な薬の投与が決まっている場合など、健康保険へ問い合わせて支払の前に「限度額適用認定証」を発行してもらいます。
申請の方法は健康保険ごとに差がありますが、必要な書類はシンプルです。
・発行申請書
被保険者(健康保険に加入している人)や発送先の情報を記載します。
どんな手術に使うのか、といったようなことは聞かれません。ある日突然何があってもいいように、何もなくても「限度額適用認定証」を発行しておいて、保険証と一緒に持っておくという方法もあります。
病院窓口で、「限度額適用認定証」を提示すれば高額療養費制度がつかえます。会計の時点で自己負担上限額までの支払いですのでお金の戻りを待つ必要はありません。
事前申請のデメリット
申請は簡単ですが、面倒だと思う方もいるようです。
- 申請することが面倒くさい
申請不要:マイナンバー健康保険証
2021年10月20日から、マイナンバーカードの健康保険証利用の本格運用がスタートしました。
マイナンバーカードを健康保険証として利用するための利用申し込みをすれば、マイナンバーカードが健康保険証になります。
マイナンバー保険証は、限度額認定証と健康保険証が一体になった保険証というイメージです。 事前申請をしなくても会計の時点で自己負担上限額までの支払いですのでお金の戻りを待つ必要はありません。
マイナンバー健康保険証のデメリット
マイナンバー保険証が使える医療機関は こちらのサイトで確認できます。マイナンバー健康保険証は病院側の普及に今後期待です。
- 限定:すべての病院や薬局が対応しているわけではない。
高額療養費制度に該当しないパターン
ここまで説明してきた高額療養費制度ですが、何でもかんでも医療費として加算できるわけではなく、使うための条件があります。 ひきつづき69歳未満の場合を前提にして解説していきます。
対象の医療に条件あり
高額療養費制度の対象は公的医療保険が使える治療や薬です。保険の効かない治療には適用できません。
- 先進医療には使えない。
- 自由診療には使えない。
先進医療とは
厚生労働省が承認した先進性の高い医療技術のことを指します。
たとえば、がんの場合は陽子線治療(ようしせんちりょう)があります。 メスを使わずにがん細胞を死滅させる治療方法で、効果があるといわれています。 この治療は保険の適用外で約300万円ほどの自己負担が必要になります。
自由診療とは
予防接種、健康診断、美容整形など治療の目的が、ケガや病気を治すものでなかったり、 日本で認められていないが海外で行われている診療などです。費用は治療によって様々です。
医療費はどこで?いくら?いつ?:該当しないパターンに要注意
高額療養費制度を使う1か月単位の医療費について、前提条件をしっかりチェックしないと損する可能性があります。 保険適用の治療費なら1か月の治療費がすべて対象になるというわけではありません。
- 1ヵ月とは月初1日から月末31日まで。月をまたいだ医療費の足し算はダメ
- 3割負担で21,000円以上ないとダメ
- 病院・入院・通院ごとに21,000円以上ないとダメ
- 扶養メンバーでも、条件に当てはまらない費用の足し算はダメ
| いつ? | 月初1日から月末31日まで | ||
|---|---|---|---|
| いくら? | 治療を受けた人1人の3割負担が21,000円以上 | ||
| 21,000円以上の計算? | A病院 | 入院 | 合計21,000円以上 |
| A病院 | 通院 | 合計21,000円以上 | |
| B病院 | 入院 | 合計21,000円以上 | |
| B病院 | 通院 | 合計21,000円以上 | |
| ・医科・歯科ごとに入院もしくは通院を分ける ・それぞれ合算して21000円以上の場合に高額療養費制度の対象になる。 | |||
| だれ? | 扶養メンバーで上記に当てはまる金額はすべて合算できる。 | ||
この条件によって損してしまうパターンについて、具体例を作成してみました。
| 病院 | 期間 | 3割負担額 | 4月の高額療養費制度になる? |
|---|---|---|---|
| A病院入院(内科) | 4月20日~4月30日 | 70,000円 | 21,000円以上 |
| 5月1日~5月15日 | 100,00円 | 21,000円以上だが、月をまたいでいるため | |
| B病院通院(眼科) | 4月1日 | 15,000円 | 同じ病院で4月の通院合計が21,000円以上 |
| 4月5日 | 10,000円 | ||
| C病院通院(歯科) | 4月10日 | 20,000円 | 21,000円未満 |
この家族が4月の高額療養費制度に合算できる金額は次の3件の医療費です。
- A病院入院70,000円
- B病院通院15,000円
- B病院通院10,000円
1か月のタイミングで損
おなじA 病院で5月の請求が100,000円あります。しかし月をまたいでいるため4月に足すことができません。
つまり5月は別に高額療養費制度を利用して自己負担限度額の8万円まで支払となります。
もしも、月初めの4月から入院していれば、A病院入院が170,000円となったため5月に再度高額療養費制度の自己負担上限額を支払う必要はありませんでした。
病院違いで損
C病院通院(歯科)は21,000円を超えていないため合算できません。
もしここでC病院から薬が処方されていて、その金額が1500円だったとします。その場合はC病院の医療費が21,500円となりますので、C病院も高額療養費制度を使うことができます。
処方された薬代 ある病院から処方された薬代は、その病院の通院の費用として治療費に薬代を足すことができます。
厚生労働省保険局:高額療養費制度を利用される皆さまへ
高額療養費制度のまとめ
いかがでしたでしょうか。ここまで年収500万円~700万円の層を基準に説明してきましたが、 高額療養費制度は2018年に大きく改正されていて、 それまで所得の高い人も一律上限8万円だったのが細分化され、所得が高い層では自己負担限度額が25万円となっています。
そのため、この制度に対する不満の声も聞こえます。 企業の健康保険組合に加入されている方は、加入組合独自制度で支払い上限を低く設定している場合があります。さらに高所得者層は税率も高いですので、医療費控除を申請することをおすすめします。
- 高額療養費制度の大事なポイント
- 「高額療養費制度」は医療費が減る。「医療費控除」は税金が減る。
- 年収約370万~約770万円の医療費の上限額は約9万円~10万円。
- 年3回以上使う場合は、さらに限度額が減る。
- 1か月は月初1日から月末まで
- 3割負担の費用が21,000円以上から利用できる
- 病院(医科・歯科)・通院・入院それぞれに21,000円以上が必要
- 薬代は処方せんを出した病院の通院に合算できる
- 扶養メンバーは世帯合算できる


