【2025年】粉ミルク補助金制度を実施している全国の自治体は?子育て支援に独自制度導入自治体も一挙に紹介
粉ミルクの出費は育児費用の中でもおむつに次いで家計に負担がかかる費用です。この記事では全国の自治体を調査し、粉ミルクの補助金や支給をしている地域をまとめました。補助金を活用にして負担を軽くしましょう。
粉ミルクの補助金・支給を行う全国の自治体一覧表
全国の都道府県庁所在地と政令指定都市を中心に、粉ミルクの補助金や支給を行う自治体を抽出しました。自治体によって支給内容と対象者が異なるので、自分が住んでいる地域の内容を確認してみてください。
岩手県盛岡市乳幼児栄養食品の支給 |
宮城県仙台市新生児誕生祝福事業「杜っ子のびすくプレゼント」 |
長野県長野市要支援母子栄養食品の支給 |
山梨県山梨市山梨市子育て用品支給事業 |
神奈川県川崎市栄養食品支給 |
愛知県名古屋市ナゴヤわくわくプレゼント事業「BABY YELL!」 |
兵庫県神戸市こべっこウェルカム定期便 |
山口県山口市妊産婦及び乳児への粉ミルクの支給 |
鹿児島県鹿児島市母子栄養食品の支給(未来を守るミルク支給事業) |
沖縄県沖縄市多胎育児世帯乳児用調製粉乳(粉ミルク)支給事業 |
表内に自分の住んでいる地域がなかった方も問題ありません。各自治体は基本的に「出産・子育て交付金」を用意しており、妊娠時と出産時に5万円ずつ受け取れます。
粉ミルクの物価指数は上昇傾向
粉ミルクの物価は物価全体の中でも、特に上昇傾向にあります。2020年基準の消費者物価指数でみると、総合指数は2020年を100とした場合110.7であるのに対して、「粉ミルク」は123となっています。(2024年12月時点)3年前と比較して、家計への負担がより大きくなっている品目といえます。
出典ː総務省│2020年基準 消費者物価指数全国 2024年(令和6年)12月分及び2024年(令和6年)平均
赤ちゃんの育児には粉ミルク以外にも固定でかかる費用があります。自治体からの援助をうまく利用して、家計の負担を少しでも減らしましょう。
粉ミルク補助金だけじゃない、全国で実施している補助金制度
粉ミルクの支給や補助金以外にも、国が実施している補助金制度があります。以下で紹介するものは国が実施している制度なので、基本的に国内であればどこに住んでいても利用できます。
出産・子育て応援交付金
日本では産前産後の経済的支援として、妊娠時と出産届出時に5万円の経済的支援をしてくれる「出産・子育て応援交付金」を用意しています。同事業は国が主体で行なっている事業で、基本的にはどこの自治体でも同様の経済的支援を行っています。
自分が住んでいる自治体に粉ミルクの現物支給サービスがない方は、出産・子育て応援交付金を活用して購入すると良いでしょう。自治体によって制度の名前や交付金以外のサービスが異なるケースもあるので、自分が住んでいる自治体のホームページで概要を確認してみてください。
対象
対象の自治体に住んでいる妊婦・産婦
内容
妊娠届出時(5万円相当)出生届出時(5万円相当)の経済的支援
出典:こども家庭庁|妊婦・子育て家庭への伴走型相談支援と経済的支援の一体的実施(出産・子育て応援交付金)
出産育児一時金
子どもが生まれたときは、1児につき50万円受け取れる出産育児一時金を活用しましょう。協会けんぽの公式サイト内にある書類に必要事項を記載し、加入している協会けんぽ支部へ提出すると、1児につき50万円が受け取れます。
お金を受け取るためには、本人確認書類や出生が確認できる書類が必要です。パートナーと一緒に書類を集めて、早めに申請してください。
対象
健康保険や国民健康保険の被保険者等
内容
1児につき50万円
※妊娠週数が22週に達していないなど、産科医療補償制度の対象とならない出産の場合は、支給額が48.8万円
出産手当金
健康保険に加入している方は、出産手当金を受け取れます。勤務先の窓口や健康保険のサイトから「健康保険出産手当金支給申請書」を手に入れて、必要情報を記入のうえ申し込んでください。
対象
・勤務先の健康保険に加入していること
・妊娠85日以後の出産であること
内容
1日あたり以下の金額を支給
【支給開始日の以前12ヶ月間の各標準報酬月額を平均した額】÷30日×(2/3)
※12ヶ月に満たない場合は別途条件あり
育児休業給付金
育児休業給付金は、育休を取得した父親・母親が利用できる給付金制度です。「育休手当」と呼ばれています。
基本的に育休は誰しも取得できる権利がありますが、育休中の賃金に関しては決まりがありません。そのため、国が賃金に関する保障を用意しています。
対象
雇用保険の被保険者が原則1歳未満の子どもを養育するために育児休業を取得した方
内容
育休を開始してから180日目までは休業開始前賃金の67%が、181日目以降は50%が支給
※支給額には上限・下限あり
出典:生命保険文化センター|出産や育児への公的な経済支援を知りたい
児童手当
児童手当とは、0歳から18歳までの児童を養育している方が利用できる制度です。 支給額は子どもの人数と所得によって異なるため、自治体へ申請する際にいくらになるか確認してみましょう。
対象
児童(0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子)を養育している方
内容
3歳未満:1人あたり月額1.5万円(第3子以降は3万円)
3歳以上高校生年代まで:1人あたり月額1万円(第3子以降は3万円)
※所得制限あり
子どもの医療費助成
子どもの医療費助成とは、病気やケガの際にかかる医療費(自己負担分)を援助する制度のことです。基本的に所得制限がなく、どのような方でも利用できる制度となっています。
対象者の年齢は地域によって異なり、15歳年度末や18歳年度末などで線引きされています。自分が住んでいる地域の条件を確認してみてください。
対象
自治体が定めた年齢の児童
内容
医療にかかる自己負担分を自治体が助成する
出典:こども家庭庁|令和4年度・5年度「こどもに係る医療費の援助についての調査」
ひとり親世帯が利用できる補助金・助成制度
ひとり親の家庭は、さらに専用の制度を活用できます。知識があるかないかで毎月使えるお金が数万円変わるので、必ずチェックしておきましょう。
ひとり親家庭等医療費助成
ひとり親家庭等医療費助成制度は「マル親」とも呼ばれる制度です。住民税を支払っている世帯は負担割合が1割になり、通院なら月1.8万円まで(年間上限14.4万円)、入院なら57,600円まで負担してくれます。
住民税非課税の世帯は自己負担なしで医療サービスを受けられます。
対象
①児童を監護しているひとり親家庭等の母または父
②両親がいない児童などを養育している養育者
③ひとり親家庭等の児童または養育者に養育されている児童で、18歳に達した日の属する年度の末日(障害がある場合は20歳未満)までの方
内容
医療保険の対象となる医療費、薬剤費等を助成
児童扶養手当
児童扶養手当は、ひとり親家庭の生活を安定させるためにお金を支給する制度のことです。都道府県や市区町村が主体となり実施しているため、地域の自治体サイトで申し込み方法を確認してみてください。
対象
18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(障書児の場合は20歳未満)を監護する父母
内容
月額最大45,500円の支給
※2人以上児童がいる場合は加算
※所得に応じて手当額は変動
ひとり親控除
ひとり親控除とは、納税者がひとり親である場合に利用できる控除のことです。控除とは金額などを引き去るときに使う言葉で、ひとり親控除では収入から35万円差し引いて所得金額が計算されます。
所得控除を活用できると、合法的に所得税や住民税を軽減できます。条件を確認のうえ、忘れずに活用してください。
対象
①その人と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人がいないこと
②生計を一にする子がいること
③合計所得金額が500万円以下であること
内容
35万円の所得控除
子育てしやすい街で使える育児家庭向けの制度
スマートマネーライフではユニークな制度を行っている自治体をリサーチしました。協賛店を募り、地域全体で割引やポイント配布を行っている自治体や、特定の物品に対する助成金が支給される地域などを紹介しています。
「子育てしやすい街で生活したい」と考えている方は、以下を参考にしてみてください。
【北海道】札幌市「どさんこ・子育て特典制度」

北海道札幌市では「どさんこ・子育て支援制度」と銘打ち、小売店や飲食店などで割引やプレゼントを受けられるサービスを用意しています。例えばドラッグストアで5%割引を受けられたり、写真館でフォトフレームをもらえたりします。
飲食店や整体院なども対象となっているので、近くで利用できる施設はないか確認してみてください。
対象
①道内にお住まいの妊娠中の方
②小学校6年生までの子どものいる方
内容
協賛事業者の特典サービス(割引やプレゼントなど)を受けられる
出典:北海道|どさんこ・子育て特典制度/利用されるみなさまへ
【東北】福島市「子育て短期支援事業(ショートステイ)」

福島市では児童の養育が困難な家庭に対して、最大6泊7日の宿泊支援を行っています。原則送迎は保護者が行うこととなっていますが、保護者の状況によっては自治体の担当者による送迎も可能です。
病気や出産、介護などがサービスの利用条件となっているため、一時的に子育てができない状況になったときは条件に当てはまっていないか確認してみてください。
対象
保護者の社会的な事由によって児童の養育が一時的に困難になった方
内容
児童福祉施設で最大6泊7日まで児童を預かる
※費用は収入によって異なる
出典:福島市|子育て短期支援事業(ショートステイ)
【関東】松戸市「幼児同乗用自転車等の購入支援・助成」

千葉県松戸市では、3人乗り自転車の安全性を確保するために幼児を乗せる自転車の購入支援を行っています。上記4つの条件を満たしていると、5万円を上限に購入金額の1/2が助成されます。
郵送で松戸市役所宛に申請する必要があるので、書類に不備がないようにしてください。
対象
1.購入日および申請日に松戸市に住んでいる方
2.申請日において2名以上の未就学児の親権を有する方、または児童扶養手当受給者で1名の未就学児の親権を有する方であり、当該幼児と生計を一にしていること
3.親権を有するすべての方が市税を滞納していないこと
4.申請者または同じ世帯の方が本事業の助成を受けていないこと
内容
幼児同乗用自転車・幼児用座席・幼児用ヘルメットの購入金額の1/2(上限5万円まで)を助成
出典:まつどDE子育て|幼児同乗用自転車等の購入支援・助成
【北陸】金沢市「多胎児家庭紙おむつ給付事業」

石川県金沢市では、2人以上子どもがいる多胎児家庭に対し、おむつを給付する事業を行っています。おむつや配送にかかる費用は一切かかりません。
対象となる家庭には、子どもが出生した月の翌々月に申し込みの案内が届きます。自治体のサイトに申請から受け取りまでの流れがPDFにまとめられているので、申し込み前に確認してみてください。
対象
金沢市に住所がある、生後3ヶ月~3歳の誕生月までの双子や三つ子等の多胎児
内容
1.毎月1回ご希望の紙おむつを無償で配達
2.子どもと保護者の方の見守りと子育てに関する情報を提供
出典:金沢市|多胎児家庭紙おむつ給付事業
【中部】名古屋市「産前・産後ヘルプ事業」

愛知県名古屋市では「産前・産後ヘルプ事業」と銘打ち、家事や育児のお手伝いを行っています。1日あたり4時間を上限とし、1時間単位で利用料を支払う形式です。産前・産後ヘルプ事業の費用は収入によって異なり、最大でも1時間あたり805円で利用できます。
家族に頼れない状態で家事や育児のサポートが必要になってしまった方は、産前・産後ヘルプ事業を利用してみてください。
対象
名古屋市内にお住まいで、妊娠中または出産後の体調不良等により、家事や育児が困難であり、かつ、昼間に家事や育児のお手伝いをしてくれる人が他にいない方
内容
調理、洗濯、掃除などの家事や授乳のお手伝いなどの援助
出典:名古屋市|産前・産後ヘルプ事業(子育て)
【関西】豊中市「カタログギフト『とよなかっ子スマイル』」

大阪府豊中市では、1万円相当のカタログギフトを配布しています。カタログギフトは育児消耗品や子育て施設利用券、玩具などと引き換えが可能です。
また、問題があったときの相談窓口などの情報も同封されており、豊中市で子育てをするために必要なものやコトが手に入ります。
対象
いずれかに当てはまる方
1.令和5年1月1日時点で市に住民登録があり、令和3年6月2日から令和4年12月31日までに出生し、市に住民登録をした子ども
2.令和5年1月1日以降に出生し、市に住民登録をした子ども
3.令和5年1月1日以降に市に転入した生後4ヶ月までの子ども
内容
以下3点を支給
1.1万円相当のカタログギフト
2.子育てに関わる行政窓口や講座の紹介 3.子育てを楽しむヒントや商品活用アイデア
出典:豊中市|カタログギフト「とよなかっ子スマイル」
【中国】倉吉市「倉吉市子育て世帯買い物応援事業」
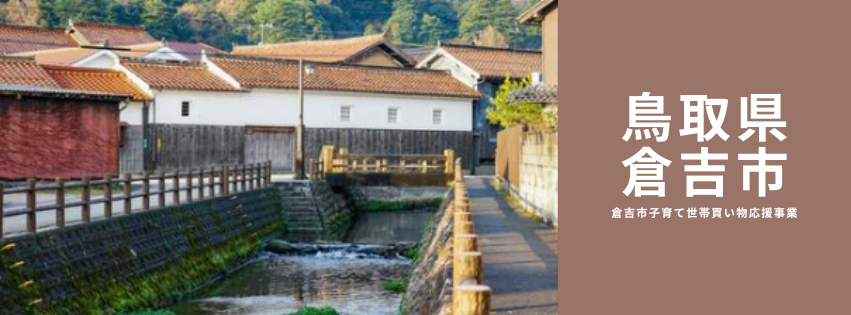
鳥取県倉吉市では「くらよし子育て応援カード」を配布し、協賛店で割引やポイントをもらえる事業を行っています。例えば家電量販店で5%オフになったり、飲食店でポイントや割引を受けられたりします。
自治体のサイトに協賛店の一覧が紹介されているので、近くで利用できる店舗はないか確認してみてください。
対象
学校就学前の子どものいる世帯または妊婦の方がいる世帯が対象
内容
子育て世帯の方が協賛店での買い物の際に割引や特典等のサービスを受けられる
出典:倉吉市|倉吉市子育て世帯買い物応援事業について
【四国】大洲市「乳児の紙おむつ購入費助成」

愛媛県大洲市では、満1歳未満の第1子を対象に、紙おむつ用の金券を5万円分配布しています。金券とおむつを交換するには、大洲市内で事業に協賛している店舗での引き換えが必要です。
また、本助成制度に申請するには、母子健康手帳と本人確認書類が必要です。あらかじめ書類を用意したうえで申し込んでください。
対象
令和5年4月1日以降に出生し、申請時に大洲市に住民登録がある満1歳未満の第1子(転入児含む)
内容
子どもが生まれた家族に対して、紙おむつを購入する際に利用できる「金券(1,000円×50枚)」を交付
出典:大洲市|大洲市の乳児へ紙おむつの購入費を助成する金券を交付します
【九州】福岡市「第2子以降の保育料無償化」

福岡市では、第2子以降の保育所や幼稚園に通う費用を無償化しています。保護者の収入に関係なく福岡市内に住んでいる方が対象となるため、多くの多子世帯にとって意味のある制度です。
手続きは原則必要なく、2人以上子どもがいる方は預け先が決まった時点でサービスを受けられます。
対象
子どもと保護者が福岡市に住んでいる家庭
内容
保育所(認可外含む)や幼稚園に通う第2子以降(0歳児~2歳児)の保育料を無償化
出典:福岡市|第2子以降の保育料無償化について
子どもの補助金について相談したいなら地域の保険相談窓口がおすすめ
粉ミルクの補助金や自治体のサービスに関する情報を知りたい方は、地域の保険相談窓口への相談がおすすめです。その地域に住んでいたり、地域住民に対して補助金のアドバイスをしたりしてきた担当者が多く、すぐに使えるお得な情報を共有してくれます。
なかでも地域に根ざしたアドバイスをもらいたいなら保険見直し本舗への相談がおすすめです。
保険見直し本舗は保険代理店なので、必要に応じて保険商品を提案されることもあります。しかし、契約は必須ではありません。無理な勧誘もないため、保険の加入が目当てでなくても気軽に相談してみてください。
| 保険見直し本舗 キャンペーンへ |
| 期 間 |
| 2025年12月1日~2026年2月28日まで |
| 条 件 |
| キャンペーン期間中に本サイトから保険相談の予約を行い、予約日が属する月の翌々月末日までに保険相談をされた方 |
| 特 典 |
| もれなくサーティーワンやミスタードーナツなどからギフトを選べる |
子育てに関するサービスは年齢制限が課されているものもあり、気付かぬうちに数万円受け取れる機会を逃してしまうケースも少なくありません。お金をかけずに数万円の価値がある情報を受け取れる可能性があるので、一度専門家に相談してみてはいかがでしょうか。

