スマホで「マイナ保険証」利用へ―日本モデル独自性は?世界の仕組みと比較してみた
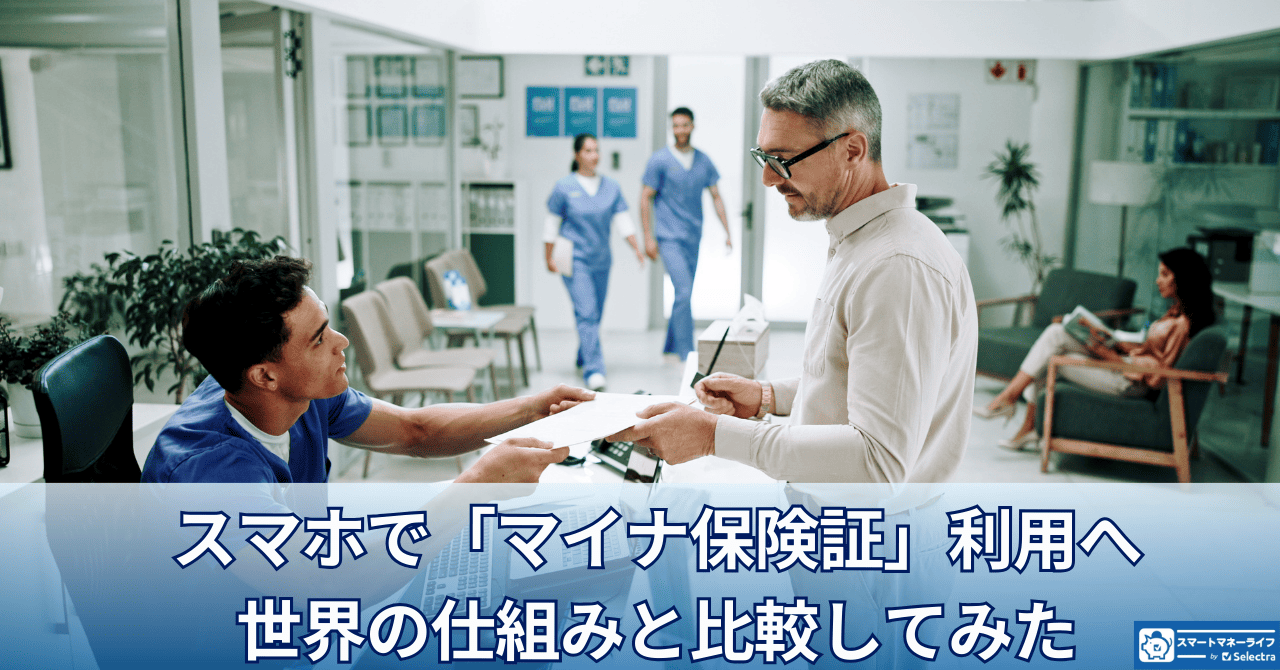
2025年12月、長年使われてきた従来の健康保険証は原則廃止され、マイナンバーカードやスマートフォンに搭載した「マイナ保険証」が本人確認の基本になります。
厚生労働省は現時点で対応しているのは全国の医療機関・薬局のうち約2割程度の約4万7000施設にとどまるとみています。しかし政府はこの改革を「利便性と効率化」を旗印に推進しています。窓口での待ち時間短縮や、過去の薬歴情報の共有による安全な診療を実現する狙いです。
しかし、国際的に見たとき、日本のスマホ版マイナ保険証は本当に便利なのでしょうか。他国のデジタル医療IDと比べてみると、日本モデルならではの強みと改善余地を検証してみました。
日本の「スマホでマイナ保険証」とは?
スマホで使えるようになる仕組み
- 基盤はマイナンバーカード:個人番号と電子証明書を備えたカードを保険証として利用。
- スマホに登録:専用アプリを通じて設定。初回はカードと暗証番号が必須で、医療機関や一部ATMでも手続き可能。
- 医療機関での利用 :病院の顔認証付きリーダーで「スマホを利用」と選び、スマホをかざして暗証番号や顔認証で本人確認。
- データ共有は同意制:診療履歴や薬の情報を医師に見せるかどうかは、利用者自身がその場で選択。
日本独自のポイント
最大の特徴は、スマホだけで完結せず「必ず医療機関の専用機器を介する」というハイブリッド型設計です。
セキュリティを最優先した日本ならではの工夫であり、二重のチェックにより安心感は高まります。しかし一方で、操作の手間や病院側の導入コストといった課題もつきまといます。
世界のデジタルヘルスID事情
世界的にみて日本のスマホでのマイナ保険証は医療のデジタル化として進んでいるのか?遅れているのか? 他国の事例と比較してみます。
エストニア ― 電子国家の先駆け
人口わずか130万人ながら「電子国家」と呼ばれるエストニア。 国民全員がデジタルIDを持ち、医療データは分散型データ連携システムを通じて相互に接続するモデルです。データそのものを集中管理するリスクを避けつつ、ブロックチェーンという技術を用いてデータの完全性と透明性を確保することで、セキュリティと利便性の両立を目指している。
- どの病院でも診療履歴や薬歴をすぐ確認
- e-処方箋が普及し、薬局でスムーズに薬を受け取れる
- スマホ認証はアプリで完結、専用機器は不要
まさに「世界一デジタル化が進んだ医療体験」を実現している国といえます
参照:e-Estonia│e-Health
イスラエル ― 全国で統一IDを活用
イスラエルでは国民全員が4つの健康保険組織のいずれかに加入し、統一された患者IDを利用します。
- 病院や診療所、薬局を横断して情報を利用可能
- 医師はどこでも患者記録にアクセスでき、誤診リスクを軽減
- データは研究や公衆衛生対策にも活用され、国の医療政策に直結
早くから医療とITを融合させた「実用重視型」の仕組みです。
参照:金融市場now│デジタルヘルスケア関連スタートアップが多数創出 2022年02月08日号
note│海外動向イスラエルのFemtech
欧州連合(EU) ― 国境を越える仕組み
EUは多国間での医療データ連携を目指し、「欧州健康データ空間(EHDS)」を整備中で、2026年までに「EUデジタルIDウォレット」を導入予定です。しかし、EUのモデルは、一国家のデジタル化とは比べものにならないほど複雑です。
「個人のプライバシーを守ること」と「データを社会のために活用すること」という相反する課題を、法制度と技術標準の両面から解決しようとしています。
- 運転免許証や健康保険カードなどをスマホに一括格納
- 国境を越えて医療データを共有可能
- 利用者が「どの情報を誰に見せるか」を細かく選べる
国境というハードルを越えるため、相互運用性に特化した仕組みを構築している点が特徴です。
参照:医療産業政策研究所│欧州におけるデータの質確保に向けた取り組み
アメリカ ― 民間主導の本人確認
アメリカには国民IDがなく、医療データは病院ごとに分断。
- 民間企業(ID.meやCLEARなど)が本人確認を提供
- 患者は病院のポータルサイトごとにデータを閲覧
- 一部の州ではモバイル運転免許証(mDL)を導入
国家主導ではなく、民間サービスが主役となっているのが特徴です。そのため統一感がないというデメリットはありますが、サービスの多様さとイノベーションに強みがあります。
参照:医薬経済│医療は最先端、国民の健康は?……『病が分断するアメリカ』
比較表:日本と海外のデジタルヘルスID
| 国・地域 | デジタルID形態 | 医療データの扱い | スマホ利用 | 特徴 |
|---|---|---|---|---|
| 日本 | マイナカード+スマホ+専用機器 | 患者の同意ごとに分散共有 | NFC+暗証番号/顔認証 | セキュリティ重視のハイブリッド設計 |
| エストニア | e-ID(カード・モバイル・アプリ) | 中央で一元管理 | スマホ完結 | 電子国家のモデルケース |
| イスラエル | 統一患者ID | 病院・薬局を横断 | 生体認証活用 | 公衆衛生や研究にも活用 |
| EU | デジタルIDウォレット(予定) | 国境を越えて共有 | スマホで一括管理 | 多国間相互運用を実現 |
| アメリカ | 民間サービス | 病院ごとに分断 | mDLや生体認証 | 国家主導なし、民間主導 |
スマホマイナ保険証-日本の独自性と課題
世界と比較して、日本システムの独自性について確認します。
スマホマイナ保険証-独自性
世界と比較して、日本は認証を重視する点に特徴があります。
- スマホ+専用機器の二重チェックによる厳格な本人確認
- 患者同意ベースでのデータ共有
- プライバシー保護重視の設計
課題はどんなところ?
デジタル化で全国民がすぐに移行できるわけではなく、高齢者やIT不慣れの方にとっては使えないという課題があります。さらに個人のプライバシーを重視すればするほど認証システムによって利便性が落ちるという問題も考えられます。
- 利便性の低さ: 高齢者やITに不慣れな人には難しく、医療機関も専用機器導入で負担増。
- 完全に浸透していない: マイナンバーカードの普及率は79.4%*
- データ連携の弱さ: 強いプライバシー保護を意識しているが、全国的な医療データ活用が進みにくい。
参照:総務省│マイナんばーカード交付状況
利用者から見たメリットと不安
上述したとおり、課題は残りますがデジタル化によるメリットは大きいといえます。
メリット
- 診察時の本人確認がスムーズ
- 「過去の診療情報に基づいた適切な処方」「重複投薬の回避」が期待できる
- 引っ越しや病院の変更があってもデータを共有できる可能性
「操作が複雑そう」、 「専用機器が故障したらどうするの?」、「毎回同意が必要で面倒」といった不安は出てきますが、スマホでのマイナ保検証は医療のデジタル化への第一歩となります。
現行モデルでまずは、高齢者や医療機関スタッフの負担感が大きくなることが予想されます。しかし 「全国民にとって一番良い形」を追い求めると、どうしても例外が増えて仕組みが複雑になってしまいますので、どこまで段階的にデジタル化できるかがカギになってきます。
まとめ
「スマホでマイナ保険証」は、日本のデジタル化の入り口といえます。
世界の制度と比較して、日本独自の強みは、セキュリティを重視したハイブリッド方式と、患者のプライバシーに配慮した同意ベースの分散モデルにあります。
よりよいシステムにするためには、システム同士のつながりを強めること。EUのように、違う仕組み同士でも安心してデータをやり取りできる環境を整えることが必要です。次に大事なのは国民の信頼を得ること。「どんなデータが、誰に、いつ見られるのか」をきちんと説明し、セキュリティを強化しつつ「使うとこんなメリットがあるよ」とわかりやすく伝えることが欠かせません。最後に、認証の手間を減らすこと。将来的にはスマホ一つで手続きが完結できるようになれば、利用者にとっても医療現場にとっても負担が軽くなることが期待されます。

