保険で貯蓄をしてはいけない4つの理由-貯蓄型生命保険より定期保険が合理的な理由とは?
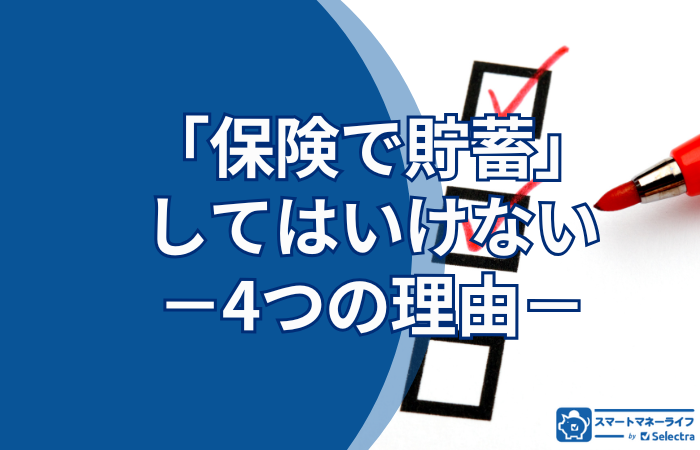
「保険でお金を貯めるのはやめたほうがいい」と耳にすることが増えました。とはいえ、終身保険や個人年金保険などの貯蓄型生命保険は、今も人気のある商品です。
実際のところ、保険で貯蓄をするのは本当にやめたほうがいいのか。この記事では、貯蓄型保険ではなく、あえて定期保険(掛け捨て)を選んだ100名への独自調査と、貯蓄型生命保険の仕組みを踏まえて、「保険で貯蓄をしてはいけない4つの理由」を解説します。
結論から言うと、「保障は保険」「貯蓄・運用は別で」と分けたほうが、家計にも将来の資産形成にも合理的です。
すでに貯蓄型保険に加入している方も、これから検討する方も、「解約すべき」という話ではなく、構造的にどこが弱点なのかをきちんと理解してから判断することが大切です。
目次
貯蓄型保険を選ばなかった人100名に聞いた「本音」
まずは、貯蓄型生命保険ではなく定期保険(掛け捨て)に加入している100名に、「貯蓄型保険を選ばなかった理由」を聞いた調査結果を紹介します。
| 🏆順位 | 貯蓄型保険を選ばなかった理由 | 人数 |
|---|---|---|
| 🥇1位 | 掛け捨てより保険料が高いから | 81名 |
| 🥈2位 | 他の運用方法(投資・預金など)を選んでいるから | 22名 |
| 🥉3位 | 戻ってくるお金(利率)が魅力的でないから | 17名 |
| 4位 | 短期間で解約すると損だから | 7名 |
(※複数回答のため合計は100を超えます)
加入している保険会社で多かったのは、次のとおりです。
| 🏆順位 | 加入している(主な)保険会社 | 人数 |
|---|---|---|
| 🥇1位 | 都道府県グループ共済 | 22名 |
| 🥈2位 | 全労災(コープ共済) | 13名 |
| 🥉3位 | アフラック | 8名 |
| 4位 | 第一生命 | 6名 |
| 5位 | メットライフ生命 | 5名 |
| 5位 | メディケア生命 | 5名 |
共済や掛け捨て中心の生命保険会社が多く、「保障はシンプルに」「貯蓄・運用は別で」という考え方を実践している層が一定数いることがわかります。
そもそも定期保険(掛け捨て)とは?貯蓄型との違い
ここで、調査対象となった定期保険(掛け捨て型の生命保険)について整理しておきます。貯蓄型保険との違いを理解することが、「保険で貯蓄をしてはいけない理由」を理解するうえで重要です。
定期保険(掛け捨て)の基本
定期保険とは、一定の保険期間(例:10年、20年、60歳までなど)のあいだに死亡した場合にのみ、あらかじめ決めた保険金が支払われる生命保険です。満期を迎えてもお金は戻らないため、「掛け捨て保険」と呼ばれます。
たとえば、子どもが就学中。パートナーが休職中などの間に「自分にもしものことがあったら、残された家族を金銭的に守る」ための保険です。
定期保険のメリット
- 同じ保障額でも保険料が安い(貯蓄型の生命保険より割安)
- 支払う保険料はすべて「保障」に充てられる
- 必要な期間だけ加入しやすく、見直しもしやすい
- 「運用」がないので商品がシンプルでわかりやすい
定期保険のデメリット
- 満期を迎えても保険料は戻ってこない
- 保険期間が終わると保障も終わる(更新時は保険料が上がることも)
一見デメリットに見える「掛け捨て」ですが、「保障」と「貯蓄」を分けて考えると、実は大きなメリットになります。
なぜなら、 定期保険で必要な保障だけ安く確保し、浮いたお金は自分で貯蓄・投資に回すほうが、トータルの手取りが増えやすいからです。
一方、終身保険や個人年金保険などの貯蓄型生命保険は、保障と貯蓄が一体化しており、「安心感」はあるものの、保険料が高くなりやすく、途中解約の弱さやインフレリスクなど、構造的なデメリットも抱えています。
ここからは、調査結果と貯蓄型生命保険の仕組みを踏まえて、保険で貯蓄をしてはいけない4つの理由を詳しく見ていきます。
理由1:保険で貯蓄すると、保険料が高くなりすぎる
調査結果の1位(81名)が「掛け捨てより保険料が高いから」でした。これは感覚的な話ではなく、保険料の決まり方そのものがそういう仕組みになっているからです。
貯蓄型の保険料は「3つの予定率」で決まる
貯蓄型生命保険の保険料は、次の3つの「予定率」によって計算されます。
- 予定死亡率: 将来の死亡リスク(保障の原価)
- 予定事業費率: 保険会社の人件費や販売コストなどの運営経費
- 予定利率: 集めた保険料を運用することで見込む利回り(割引率)
同じ死亡保障1,000万円でも、貯蓄型保険は「解約返戻金」や「満期金」を上乗せするため、掛け捨ての定期保険より保険料が高くなります。
具体的なイメージ:同じ1,000万円の保障でも、ここまで違う
たとえば、30代で「万一のときに1,000万円の保障が欲しい」というケースを考えてみます。
- 定期保険(掛け捨て): 月額 1,000〜3,000円程度
- 終身保険(貯蓄型): 月額 10,000〜40,000円程度になることも
毎月の差額は1万円以上になることも珍しくありません。
この差額を20〜30年間、投資信託などで運用した場合、将来の資産額は数百万円単位で変わります。
調査で多くの人が「掛け捨てより保険料が高いから」と答えたのは、感覚的な“高い・安い”だけでなく、 「保険料差額を別の運用に回したほうが合理的」と理解している人が増えていることの表れとも言えます。
参考:O社定期保険42歳男性 死亡保険金1000万円 2,120円/月(10年満了)
O社終身保険保険42歳男性 死亡保険金1000万円 41,920円/月(15年払済)
理由2:貯蓄型保険の利率は「インフレ」に勝ちにくい
調査の3位は「戻ってくるお金(利率)が魅力的でないから」(17名)。
ここでポイントになるのが、貯蓄型保険でよく出てくる「予定利率」です。
予定利率=「高利回り」ではない
貯蓄型生命保険で重要な、予定利率について解説します。
- 将来の保険金・解約返戻金の支払いに必要な金額を
- 「運用で増えるはずの分」を見込んで
- あらかじめ保険料から割り引くための“割引率”
つまり、 「保険会社が運用で増やせると見込んでいる利率」であり、 「銀行預金より明らかに高利回り」という意味ではありません。
特に円建ての終身保険や個人年金保険では、 超低金利時代に設定された予定利率がそのまま使われている商品も多く、 現在の定期預金や投資商品の利回りと比べると見劣りするケースもあります。
インフレが続くと「実質的な価値」は目減りする
仮に年率2%のインフレ(物価上昇)が続いた場合、30年後の100万円の価値はおよそ55万円程度にまで下がると言われます。
貯蓄型保険の返戻金は「額面上」は増えていても、物価に負けて実質的な購買力が減ってしまうリスクがあります。
特に、定額型の終身保険・養老保険・個人年金保険は「受け取る金額が契約時にほぼ確定している」ため、 インフレによる価値の目減りリスクを自分で負うことになります。
理由3:途中で解約すると「ほぼ確実に損」になる
調査の4位は「短期間で解約すると損だから」(7名)でしたが、 実はここが貯蓄型保険最大の落とし穴と言っても過言ではありません。
解約返戻金は「最初の10〜15年」は元本割れが当たり前
一般的な貯蓄型保険では、加入してすぐ〜数年のあいだに解約すると、 解約返戻金は払込保険料総額を大きく下回ります。
- 加入〜5年:返戻率 20〜40%程度
- 10年程度:返戻率 50〜80%程度
商品によって解約返礼率の差はありますが、 「満了前は、支払った保険料総額より戻り金額は少ない」という構造は共通です。 解約返戻金は契約している保険の解約返戻金は加入前、もしくは各保険会社の契約情報から確認ができます。
住宅購入・転職・出産・介護など、想定外のライフイベントでお金が必要になったときに、解約すると損失になる可能性があります。
現代のライフスタイルと「貯蓄型保険の硬さ」は相性が悪い
今は、転職・独立・海外移住・家族構成の変化など、ライフスタイルが大きく変化する時代です。
- 「とりあえず入っておこう」と長期の貯蓄型保険に入る
- 数年後にライフイベントでお金が必要になり、解約せざるを得ない
- 結果的に「掛け捨てより高い保険料を払って、返ってくるお金は少ない」という状態に
こうした状況を避けるためにも、「いつでも解約しても大きく損をしない」定期保険+自分で運用する資産という組み合わせのほうが、柔軟性の高い設計と言えます。
理由4:保険は「運用商品」として設計されていない
調査の2位「他の運用方法(投資・預金)を選んでいるから」(22名)は、非常に本質的な理由です。
貯蓄型保険は「保障+貯蓄」を1つのパッケージにした商品
終身保険・養老保険・個人年金保険・外貨建て保険・変額保険などの貯蓄型生命保険は、 いずれも「保障」と「貯蓄(運用)」を1つのパッケージにした商品です。
そのため、次のようなコストがすべて保険料に含まれます。
- 死亡保障などの保険そのもののコスト
- 保険会社の事務・人件費・営業コスト
- 資産運用にかかるコスト
一方、投資信託やETFなどの金融商品は、「運用」部分に特化しており、単純な運用コストだけを比較すると、 貯蓄型保険よりはるかに低コストであることが多いのです。
外貨建て保険・変額保険の「運用リスク」は誰が負っている?
外貨建て保険や変額保険は、「高い利回りが期待できる」と紹介されることもあります。しかし、その裏側では、
- 外貨建て保険:為替リスクを契約者が負う
- 変額保険:株式・債券などの運用リスクを契約者が負う
という構造があります。
| 商品 | 運用リスクの所在 | 利率保証 | 収益性の上限 | 安全性の 相対評価 | 将来の増加余地* 相対評価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 終身保険 | 保険会社 (金利・運用) | あり (予定利率) | あり (予定利率) | 高い | 低い |
| 外貨建て保険 | 契約者 (為替リスク) 保険会社 (外貨金利) | あり (外貨ベース) | 外貨金利水準 | 中程度 | 中程度 |
| 変額保険 | 契約者 (投資リスク) | なし (最低保証を除く) | なし (市場連動) | 低い 〜中程度 | 高い |
*運用成果によって返戻金・保険金が増える度合い
それでも貯蓄型生命保険が向いている人は?
ここまで読むと「貯蓄型は全部ダメなの?」と思うかもしれませんが、そうとは限りません。
一定の前提条件のもとでは、貯蓄型生命保険が有効な選択肢となるケースもあります。
貯蓄型生命保険が向いている人の例
- 自分ひとりでは絶対に貯金が続かない人(強制的な積立が必要なタイプ)
- 投資がどうしても怖く、値動きに耐えられない人
- 相続対策として一時払終身保険を活用したい人
- 学資保険など、教育資金を「用途とタイミングを決めて」積み立てたい人
こうしたケースでは、「多少コストが高くても、強制力や分かりやすさを買う」という意味で、貯蓄型生命保険が選択肢になり得ます。
ただしその場合でも、
- 解約返戻金の推移(どのタイミングで元本を超えるか)
- 予定利率や運用リスクの所在
- インフレによる実質的な価値の目減り
といったポイントは必ず確認したうえで、「無理なく続けられる保険料か」「他の手段と比べて納得感があるか」をチェックすることが大切です。
まとめ|保障と貯蓄を分けるだけで、お金の選択肢が広がる
最後に、「保険で貯蓄をしてはいけない4つの理由」をあらためて整理します。
- 保険で貯蓄すると、保険料が高くなりすぎる
掛け捨てより保険料が高く、差額を別の運用に回したほうが合理的。 - 貯蓄型保険の利率はインフレに勝ちにくい
予定利率は「高利回り」ではなく、物価上昇による価値の目減りリスクを抱える。 - 途中で解約すると「ほぼ確実に損」になる
解約返戻金は長期間、払込保険料総額を下回り、ライフイベントの変化に弱い。 - 保険は「運用商品」として設計されていない
同じリスクを取るなら、投資信託や外貨預金などのほうが低コストで透明性も高い。
保険は、本来「万一のときに家族を守るための道具」です。一方で、貯蓄や投資は「将来に向けてお金を増やすための道具」です。
この2つを一つの商品にまとめたのが貯蓄型生命保険ですが、まとめた結果として「どちらも中途半端」になりやすいという側面があります。
- 保障はシンプルな定期保険(掛け捨て)で必要額だけ確保する
- 貯蓄・投資は、目的やリスク許容度に応じて自分で商品を選ぶ
という「保障と貯蓄を分ける考え方」が、家計にも将来の資産形成にもプラスに働きます。
もし今、貯蓄型生命保険に加入している方は、「すぐに解約すべき」という話ではありません。
まずは自分の保険料・返戻金・予定利率・解約した場合の損益を一度整理し、掛け捨て保険+別の運用方法に切り替えた場合と比較してみることをおすすめします。
「保険で貯蓄」は、なんとなく安心に見える選択肢ですが、仕組みを知ると、もっと自由で合理的なお金の使い方が見えてきます。
あなたと家族のライフプランにとって、最適な組み合わせを冷静に選んでいきましょう。
